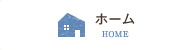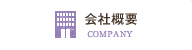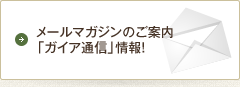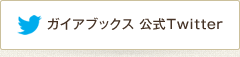ニュース/トピックス
第1回 山本博先生のスペシャルワイン情報【長野県】
- 2012.10.10

-
山本博先生から 企画に寄せてスペシャル情報 ♪
≪第1回≫長野県ワイン情報編




明治政府のワイン産業奨励策に応じて長石でも早くも明治5年から松本市の百瀬二郎や豊島新三郎他数軒がワイン造りを始めたが、山梨県とちがって果樹県にこそなったが、すぐには葡萄県にはならなかった。そのうち塩尻村で頭角を現した「巴印葡萄酒」を小泉八重蔵が発展させ、それが後の桔梗ヶ原の成功につながっていく。
なにしろ長野は西に飛騨山脈、南西は木曽山脈、南は赤石山脈と全県これ山、山、山である。
耐寒栽培技術が未発達の当時、葡萄栽培・ワイン造りと考える人は少なかった。
その迷信を破ったのが「小布施」の曽我彰彦である。小布施は長野市の少し北東になる古い街道町で、ここの日本酒「泉滝」メーカーの息子だった。子供の頃から酒に関心を持ち山大学の発酵生産学科(現・生命環境学部生命工学科)を卒業した後、新潟のカーブドッチに修業に行ったりした。しかしそれだけではあきたらず、1997年単身フランスのブルゴーニュへ行く。幸いアルベール・ビジョー社に雇われ、よく働くのが目にとまり名門、酒造家ドメーヌ・ロン・デパキで働くことが出来た。当時フランスの名酒造家で実地に修業してきたのが彰彦ひとりだっただろう。平成10年帰国するや適地を選んでブドウ畑を開発、古い日本酒醸造具を工夫してだましだまし使い、徒手空拳でワイナリーを立ち上げた。日本の酒類業界でも知る人はほとんどいなかったが、山梨県で行われている国産ワインコンクールで並みいる国産メーカーを尻目に見事金賞を取ったので大騒ぎになった。以後今日まで長野県のワイン醸造界できらりと光る存在になっている。
もうひとりの異色は「サンクゼール」(斑尾高原農場)長野市の北に芋川という面白い名の地名があり、JR信越線牟礼駅で下車しタクシーで行ける。戸隠高原か野尻湖の東南、スキーで知られる斑尾山の麓。池袋で有名な食品関係業者の長男、久世良三は慶応大学卒のスポーツマン。スキーの選手だったから信州じゅうのスキー場を夫婦で滑りまくっていた。そのうち妻の興味もあって野尻湖フルーツジャムの製造販売を始めた。ヨーロッパ旅行をしたとき農村と文化の関係に触発され、日本でワインを造りたくなった。北信地区を選び、地方行政当局に相談したところ三水村を紹介され、そこで見かけた小高い丘(町営「ふれあいの里」の上)を買収。そこへ一流店なみのレストランを建てた。畑は近くのリンゴ園が廃園になったところを買った。ゆるやかな傾斜西畑は8ヘクタール。ブドウの植え付けと栽培には苦労したが、幸いに浅井昭吾に依頼して整えなおした。すべてギヨー式の垣根仕立て。免許を取ったのは8年後。現在畑は10ヘクタール(3万坪)で当時日本でこれだけの個人畑をもっているところはそうはなかった。しかも山奥である。妻がクリスチャンだったから、隣りにチャペルを建てたが、何が幸いになるかわからないもので、レストランの名声をききこんでくる客に加え、このチャペルで結婚式を挙げたがったヤング層をひきつけた。植えたブドウはシャルドネ主体。現在は建物を改築したりして地域の観光スポットになっている。若い技術陣が奮闘。ワインも他の有名メーカーのものに引けを取らない。
「桔梗ヶ原メルロー」 現在、長野県はワイン用ブドウ栽培に関するかぎり山梨県を抜いた。日本国産ワインコンクールで山梨県の大手メーカーがいつもトップクラスの座を占めている。すべて醸造所こそ山梨にあるが使っているブドウは長野県産のものが多い。そうした長野県の発展のきっかけになったのが桔梗ヶ原なのである。
桔梗ヶ原は塩尻の西南、東京から諏訪湖や岡谷の奥手になる。(塩尻インターで降りて、木曽街道に向かうと塩尻市の町はずれ)海抜約700メートル。古代に松本盆地の沈降により周辺山地の浸食が進む中で特有の地質。(上はローム層、その下部は粘土質、その下は砂礫層)が形成された。ここはもともとは果樹栽培用の土地だった。これを長野県ワインの草分け的存在に一変させたのは林幹雄と浅井昭吾という二人のキャラクター。
いろいろ事情があって、ここはサントリー社の「赤玉ポート」と大黒葡萄酒(現メルシャン)の甘味ブドー酒の大原料供給地になっていった。メルシャン社は自社畑を持たなかったからワイン事業の拡大方針のため、全国各地に栽培適地を探していた。そうした中で、偶々日本ワインの始祖と言える浅井が林家の「五一ワイン」で外国品種メルローを栽培しているのに目をつけ、これへの転換をはかった(井筒ワインもサントリーから助けてもらったメルローを栽培していた)。ブドウ栽培農家を集め時流の変化を説き、従来のコンコードやナイアガラを引き抜きメルローに植え替えることを提案・説得した。ブドウは植え替えてから3年から5年たたないとまともな実をつけない。その間は無収入になるから農家達は容易に承諾しなかった。そこで従来の樹はそのままにして、その横にメルローを植え、それが充分育ったら、従来の品種ブドウを引き抜くという方法で皆が納得した。新品種メルローの栽培は寒冷対策その他難問が続発したが諸工夫で乗り切った。
フランス・ボルドーの赤品種の代表はカベルネ・ソーヴィニヨンでそれを補完するのがメルローである。日本では風土の関係でカベルネ・ソーヴィニョンはうまく育たない。多くの試栽培が行われてきたが挫折したところが多い。ところが桔梗ヶ原のメルローの方はすくすくと育った。これを使ったメルシャン社のメルローワインは大成功。業界を驚かすと同時に栽培家の頭の切り替えに役立った。メルローは冷地・多湿のところでも育つ。ワインにするとカベルネ・ソーヴィニョンの持つ力強さ迫力の点では劣るが、そのかわりに飲みよい赤ワイン出来る。日本の多くのワイン生産者達は外来ワイン専用ブドウ品種(ことに赤)は日本の風土では難しいと考え、川上善兵衛が考案開発した交配種、マスカット・ベリーAを使うのがほとんどだった。ところがこのブドウは日本で栽培するのは容易だがワインに使うと味の面で難点がある。メルシャン社の大成功を見て赤ワイン用にメルローを使うところが激増し、今や日本産メルローを使うところが激増し、今や日本産メルローワインは外国産のものに見劣りがしないものに育ちつつある。ちなみにメルシャン社は北信で栽培したシャルドネでも成功している。
桔梗ヶ原は「五一わいん」で新展開したが、ここには堅実なワインを造り続ける技術と意欲を持つ「井筒ワイン」があることは忘れられてはならない。
「ヴィラデスト」
日本で最もユニークなワイナリーと言えばヴィラデストである。それは玉村豊男というひとりのキャラクターの創意と努力が生んだものである。
長野県でも「小諸なる古城のほとり遊子悲しむ」と歌われた小諸も含む千曲川流域は長野県でも一風変わった地方である。その小諸の少し西の東御市(旧小県郡東部町)で孤島のような存在でありながら精彩を放っているのがこのワイナリーである。(スキー場菅平へ登る入口。マンズ社の「小諸ワイナリー」からいくらも離れていない)
毎日新聞日曜版に美しい野花の淡彩画を描き続けていたエッセイスト玉村豊男は、1991年夏に東部町(現・東御市)に移住した。生粋の江戸っ子だった玉村がこの地に住むようになったのは、もとはと言えば妻がハーブ中心の園芸に夢中だったからである。ここでワインを造ろうと思いついたのは当時日本で売られているデイリー日常酒としてのワインはあまりぱっとしなかったからである。玉村は東大在学中パリ大学言語学研究所に留学したり、ヨーロッパ諸国をツアーコンダクターとして廻った経験があり、ヨーロッパの生活になじんでいた。玉村の書いた「パリ旅の雑学ノート」を読むとその着眼点の鋭さと蘊蓄に驚かされる。言うならばワイン漬けになった生活をしていたキャリアがある。また宝酒造のTAKARA酒生活文化研究所の所長を務めていた。飲む方では人後におちないがワイン造りについてはズブの素人だった玉村は、詳細綿密な計画をたてた。ブドウ栽培の実地基礎を学びながら最初の菌を植えるのに約三年、ブドウがまともな実を実らせるのに三年、そのブドウから自家製ワインを造るのに三年というようにである。このあたりは巨峰ブドウの名産地だが、ブドウはヨーロッパのワイン醸造専用品種しか植えない。その選択と栽培方法は甲府の植原研究所の植原宣紘に膝詰め談判で教わった。選んだ品種はカベルネ・ソーヴィニョン、ピノ・ノワール、ドイツ種など。フランスに知る人ぞ知る『不可能のワイン』という本があり、その本を読んで挫けそうになる気持ちに鞭を打った。実際にやってみると難問の続発、その苦闘の物語は『私のワイン畑』扶桑社、後に中公文庫に生き生きと描かれている。マンズ社の志村技師、メルシャンの浅井昭吾も手伝いに来てくれた。
すべてが順調に動き出したところ驚天動地の事態が発生。宝酒造がワイン事業に進出する計画をたてたので、東部村を推奨し着々と準備を進めていたが、平成12年、会社の経営方針が変わり突然中止になったのである。開発に協力してくれた多くの関係者に迷惑をかけることは言うまでもないが、玉村自身も畑を買い足していた苗木数千本が宙に浮くことになった。身体ここに窮した玉村は、それなら自分で自分のワイナリーを造ってやろうと決心。難問が百出したが、とりわけ問題は二億円という必要資金。ところが絶望的と思っていた農林漁業金融公庫から一億円の融資が受けられることになった。窮余の末考えついたことは会員を募ってお金を集めることだった。50万円預かって10年間で50万円分のワインを頒布するというプロジェクト。そんな虫のいい話と笑われたが、いざやってみると玉村の人徳もあってかわずか1ヵ月で80名が入会、100人の定員を超える120名が集まった。
かくて装い新たに建ち上がった見晴らしのいい丘の上のワイナリーは、おいしい料理とパンを出すテラスレストラン、玉村の水彩画を含むブティック風ギャラリー、規模こそ小さいがコンパクトに整った醸造室、そしてハーブ・ガーデン。シャルドネとメルローを主体にした3ヘクタールの垣根仕立のブドウ畑も見事。ワインだけでなく地元のリンゴを使うシードル、玉村が考案した装置から生まれるグラッパも出している。話を聞いて訪れる客は絶えず、休日などは昼食は二回転、まさに大成功!ここは単なるワイン製造所でなく文化の香り高き総合文化施設、カルチュラルセンターなのだ。生きとし生けるものが生命の賛歌を歌いあげる場所なのだ。
今や玉村の業績に心奪われ、ワイン造りを志す者が数名、ヴィラデストを囲んでミニ・ワイナリーを立ち上げようとしている。まだ小粒だが新ワイン生産地の誕生なのだ。こうした状況に応じるため、その将来を考え、玉村は千曲川ワインバレー構想をたてている。
最新の3件
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年6月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年11月
- 2021年9月
- 2021年7月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年9月
- 2019年7月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年8月
- 2018年4月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年9月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年4月
- 2014年2月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月